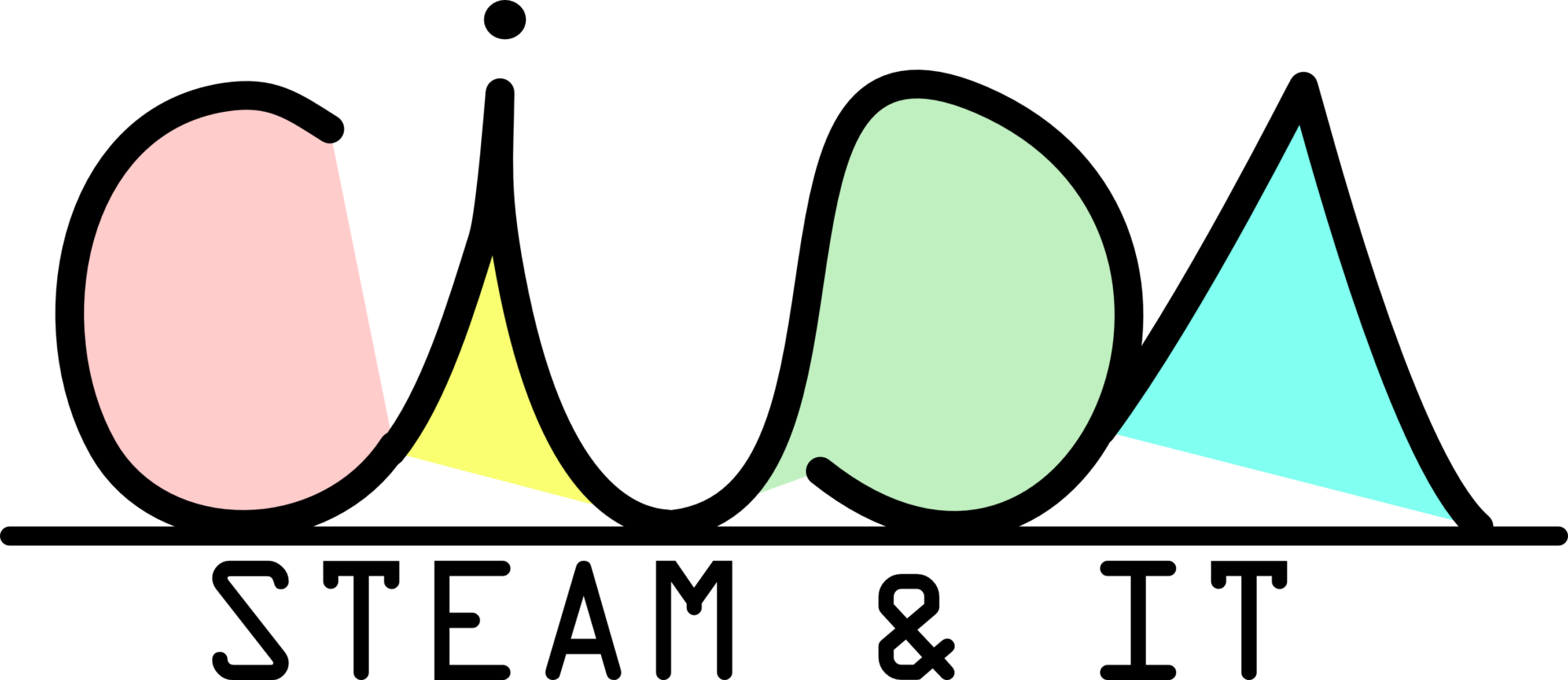TechCIDAの由来
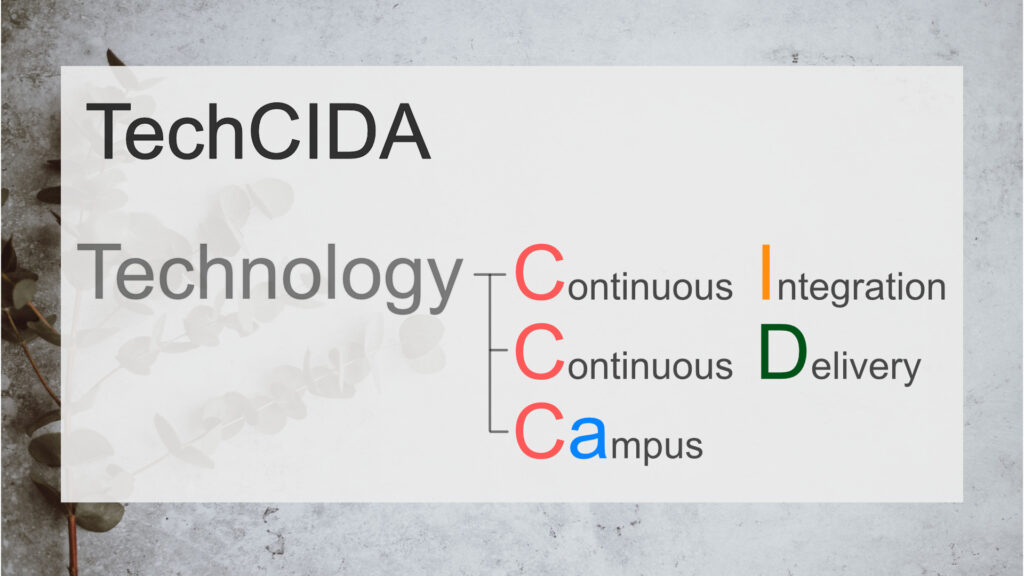
TechCIDA(テックシーダ)とは、「TechnologyをCI/CDするCampus」という意味が込められています。
CI/CDとはソフトウェアエンジニアリングの用語であり、CI:継続的インテグレーション/CD:継続的デリバリーの略称となります。
ソフトウェアの変更をテストし、自動で本番環境に適用できるような状態にするプロセスです。
当教室で学んだ「Technology」を「CI/CD」継続的に理解(ビルド)し、自分のものに(デプロイ)する「キャンパス」(学びの場)にできればと思っています。
Mission
宮崎のIT人材育成

テクノロジーの進化は止まることを知りません。
私たちは、この変化に柔軟に対応し、宮崎県をIT教育の先駆けとして位置づけることを目指しています。地域の若者たちに最先端の技術を学んでいただくことで、地域経済の活性化と持続可能な発展を目指します。
そのために、テクノロジーの力で未来を切り拓く教室として、地域社会と密接に連携しながら、若い世代から大人まで、幅広い層の人々にITスキルを身につけてもらうための教育プログラムを提供します。
講師紹介
【経歴】
宮崎市出身。高校卒業後に宮崎を離れ、岡山大学 工学部へ入学。
大学時代に家庭教師、キッズスイミングコーチ、学生サークルを立ち上げ学童や子供向け展示会出展などの活動を実施。
学士・修士論文ではロボット分野の 心筋細胞把持マイクログリッパ、 急冷式マイクロリアクタを研究。
岡山大学大学院を卒業後は、大阪・東京でソフトバンクエンジニアとして活動。
全国の法人ネットワークの保全運用を担当。
現在はフリーランスエンジニアとしてリモートで活動中。
本職はネットワーク/AWSクラウドエンジニア
TechCIDAを立ち上げた思いについては コチラ
【資格】
工事担任者(AI/DD総合種)
AI G検定
IoTアドバイザー
AWS CLF
AWS SAA-02
Azure Fundamentals
SNSマーケティング検定
Google サイバーセキュリティ プロフェッショナル
Google データアナリティク ス